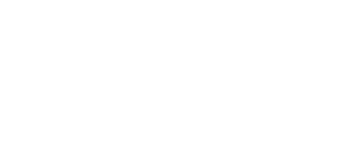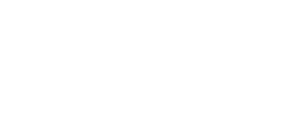令6 1学期終業式より(R6/7/19)「君たちはどう生きるか」
六月十日・十一日に、本校最大の学校行事の…
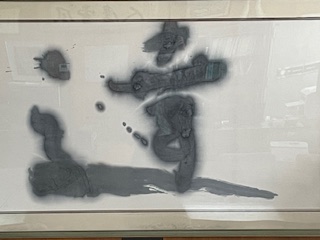
令6 1学期始業式より(R6/4/9)「一人一人が代表選手!東高は青春選手村」
昨日より安城東高校は新1年生を迎え、いよ…

令5 3学期終業式より(R6/3/19)「過去の輪島市交流と来年度の国際交流」
令和5年度が終わろうとしています。みなさんの令和5年度は充実していたでしょうか。それとも不完全燃焼だったでしょうか。3月1日の卒業式で、私は3年生に対して次のようなことを言いました。「現状に満足や絶望すること無く、常に人生の道の途中だという認識の中で、しっかり前を向いて進んでいってほしい。」同じ言葉を今、1・2年生のみなさんに贈ります。4月からの新学年に向けて、しっかり前を向いて前進して下さい。
さて、これを見て下さい。これは式典や表彰で使われる賞状盆です。この賞状盆は黒く塗られていますが、どのような方法で塗られていると思いますか。これは能登半島の輪島市の伝統工芸である輪島塗りでできており、1995年、平成7年に輪島市から本校に感謝の意を込めて寄贈されたものです。今、輪島市がある能登半島は大変なことになっており、以前みなさんにもメールとHPでお知らせしましたが、本校同窓会の11回生の方々が中心となって、1月22日(月)に4トントラックで支援物資を輪島市に届けました(リンク:本校同窓会が能登半島輪島地域へ物資等を支援しました)。その様子は、中日新聞やケーブルテレビ「キャッチ」でも報道されました。また、みなさんには、募金の協力をしていただきました。ご協力ありがとうございました。本校と輪島市との交流は40年以上の歴史がありますが、その歴史は同窓会HPの中にある「わじま・あんじょう友の会」(リンク:わじま・あんじょう友の会トップページ…

「碧海野だより」第154号(3月1日発行)より「冠沓(グローカル)」
ー『碧海野(おうみの)だより』(安城東高校PTA通信)第154号(3月1日発行)よりー
「冠沓(グローカル)」
第四十六回生のみなさん、そして保護者の皆様、ご卒業本当におめでとうございます。
2学期終業式でもお話ししました(HPにも載せてあります)が、これからは情報AI革命が更に進み、変動、不確実、複雑、曖昧な社会を生きていかなければなりません。しかしそのような時代だからこそ、逆に人間の繋がりが重要だと思います。その意味でも、三学期始業式でお話ししたように、安城東高校の同窓という縁や繋がりを、自分の持っている資源の一つとして大事にしていって下さい。
さて、私が以前作った「沓冠折句(くつかぶりおりく)」の歌を、「馬の鼻向け」としてみなさんにお贈りします。(「馬の鼻向け」とは古典『土佐日記』の「門出」にも出てくる言葉で、「はなむけ」の語源となったものです。ぜひ調べてみて下さい。)「沓」は現代の靴につながるもので、履き物のことです。「冠」は地位…

令5 第46回卒業証書授与式より(R6/3/1)「on the way 人生は三寒四温」
式 辞
寒かった冬の日々に比べて、少しずつ暖かい日が入り混じるようになってきました。「三寒四温」という言葉がありますが、それは、寒い日が三日、暖かい日が四日というように、寒い日と暖かい日を繰り返しながら、次第に春になっていくという、ちょうど今の季節の気候を表す美しい日本語です。今年は2月の下旬から、日ごとの寒暖の気温差が、やや大きかったかもしれませんが、確実に春は近づいてきています。
そんな季節の変わり目の中、弥生三月早春の今日の良き日に、来賓の皆様のご臨席を賜り、愛知県立 安城東高等学校 全日制課程 普通科の卒業式を無事挙行できますことを、心より感謝申し上げます。
また、保護者の皆様、お子様のご卒業、誠におめでとうございます。教職員一同、心からお祝い申し上げます。まだ子育てが終わったわけではありませんが、高校卒業は、お子様の自立に向けた一つの大きな節目として、少しほっとされたのではないでしょうか。私も今、自分の子供が高校を卒業した時のことを思い返すと、嬉しいような寂しいような、長かったようなあっという間だったような、そんな感慨に浸ったことを思い出します。
さて、四十六回生のみなさんは、三年前の令和三年四月に、安城東高校へ入学してきました。入学前の中学三年生の時には、その年から本格化した、新型コロナウィルスによる社会的混乱の中で、休校に続いて学校行事の中止や延期が相次ぎ、とても不安な受験生生活を送っていたでしょう。そんな不安な生活が続いている最中に、みなさんは縁あって本校へ入学したわけですが、みなさんは今、今日までの三年間の高校生活をどう感じているでしょうか。努力が実を結び、充実していたでしょうか。逆にうまくいかずに不充分だったでしょうか。それとも努力をしようとしても、コロナのせいで、せっかくの高校時代、青春時代が不完全燃焼だったと感じているでしょうか。
充実していたのであればそれに越したことはありませんが、しかし、どのような高校生活であっても、それは英語で言うon…

令5 3学期始業式より(R6/1/9)「創立50周年事業について」
短い冬休みが終わりました。令和6年の始ま…

令5 2学期終業式より(R5/12/22)「総合的な探究の時間[GLS]について」
気が付けば令和5年も残りわずかとなりまし…

令5 2学期始業式より(R5/9/1)「Done is better than perfect」
長いと思っていた夏休みも終わってみればあっという間でした。事前に立てた夏休みの計画は思い通りに実行できましたか?特に3年生の人、どうでしたか?恐らく完璧に実行できた人は少ないでしょう。できなかった人はすぐにできなかったことの検証と修正実行をして下さい。大事なことは、思い通りいかなかったことの検証と修正実行です。
「完璧を目指すよりまず終わらせろ」とは、Facebook創業者マーク・ザッカーバーグ氏の言葉です。原文は「Done…

令5 1学期終業式より(R5/7/20)「生成AI時代に必要な2つの能力」
今日はあらかじめ用意してきた文章がありま…

令5 1学期始業式より(R5/4/7)「秒速50cmと秒速11.2kmの視点」
秒速5センチメートルとは何の速さのことかご存じですか。それは桜の花びらが無風状態で散る時のスピードだそうです。この言葉は映画「すずめの戸締まり」「君の名は。」で知られる新海誠監督が2007年に作った短編映画のタイトルにもなったので、ご存じの方も多いかと思います。今年はちょうど今が桜が散っている時期なので、このことを思い出しました。でも実際には桜が散るスピードは秒速5センチよりももっと速いような気がします。秒速5センチはかなり遅いですよ。実はこのネタはずっと以前に言ってた人がいて、歌手のさだまさしさんが1993年のコンサートトークで語っていたもの(Live…