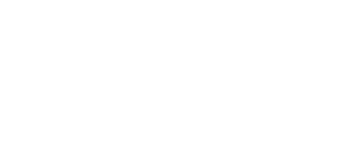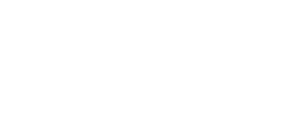私の原風景(1)~山
半世紀以上生きてきて、いまだに、「高校時代は…?」と自分に問いかけてしまうのは、高校教師としての宿命なのだろうか。それとも、何か特別の思いがあったからなのだろうか。現実と理想のはざまで、満たされない何かを感じつつ過ごしていたその時の記憶は、ある出来事を想起させる。それは、現実の生活に満足できず、かといってなすべきことの解を見出すこともできなかったその時代特有のものであろう。
私は中学校・高校と部活動に属していたものの、これといった成果を残すことができず、満足のいくものではなかった。高校3年生の時には、「大学でしかできない、自分一人ではできないことをやろう」と決めていた。そのひとつが登山だった。高校2年生の時に、山岳遭難のニュースを見たことがきっかけだ。それは、ロッククライミングで岩場に宙吊りになった遭難者を救出する映像で始まった。本当に衝撃的な映像だった。「そんなに危険なことまでして挑戦するのはきっと何かあるのだろう?」、「なぜ人は、山に登るのか?」。これまで山に登ったこともない私が、その時以来、そう問い続けること以外に答えの見つかりそうにない世界に入ってみたいと思うようになった。
大学入学後、山岳系の体育会サークルに入部すると、先輩から「目上の人と話す際の言葉遣いも知らない」とたしなめられ、「大学4年生は、神様だ」と教わった。大学6年生の先輩もいたから、本当に神様だと思った。合宿は春夏秋冬、毎日マラソンに始まるトレーニング、たまに砂袋をザックに詰め込んで、校舎棟の非常階段の上り下りをする生活が始まった。
夏合宿では、10日間余りのテント生活をする。8人前後でパーティーを組み、北アルプスや南アルプス、北海道大雪山系など、行きたい山域へ向かう。夏山では、午後に発生しやすい雷を避けるため、毎朝2時頃には起床する。起床後すぐに飯炊きから始め、その後、朝露をしっかりと吸収して重くなったテントを撤収し、次のテント場に向けて10時間近く、40kgもの荷物を背負って歩かなければならない。先輩からの差し入れのスイカまで持たされた。これまで生きてきて、こんなに辛いことはないと思ったが、とにかく歩かなければ終わらないし、歩くことしかない毎日だった。
山の朝はいい。空気が澄んでいる。本当に空気が美味しいと感じる。厳冬期の山の、突き刺すような寒さも格別だ。冬山では、雪洞を掘ってそこで一夜を過ごし、滑落停止の雪上訓練をしながら山行をした。髪の毛も樹氷状態、白髪になる。氷点下20度の世界、テントの中に入れたポリタンクの水も凍るので、それを股の間に挟んで寝る。不思議と下山してしばらくするともう一度登りたくなる。山行中のあの辛さは、いつもどこかに吹き飛んでいた。
「山では自分の行為の質が変わるように、思考の質も変わる」と私に気付かせてくれたのは、フランス哲学の研究者である串田孫一の著書『山のパンセ』*である。串田は、東京外国語大学で哲学を教える傍ら、同大学山岳部長を務めた「行動する哲学者」である。登山家としては、戦前の谷川岳・堅炭岩で冬期登攀の記録を持っている。その串田が2005年(90歳)に亡くなってから、20年近く経とうとしている。
この書を初めて手にした時、「パンセ」(フランス語で「思考、思索」、17世紀のフランスの哲学者パスカルが書き留めた同名の著書がある)とは、随分と大袈裟な本の名前だと正直思った。そもそも私にとって山に登る行為は、「景観を楽しみながらも、ひたすら歩き、予定時刻までテント場に到着し、食事を作り、次の日のことを考えて早く寝ること」だったのであり、そのことと思索とは無関係に思えた。今では、時あるごとに読み返し、たまの山行に持参するのだから、串田文学の代表作とされるこの作品は、私にとって特別の意味をもつということだろう。
串田は、『山のパンセ』の中で、次のように述べる。
「山へ来て、普段のからみついて雑多なものをあっさりと忘れ去ることの出来る時が、かつての私にはあったような気もする。尾根の急な草原に身をうめて、そこで考えることは、人々の言う雑念とは遠く、地上よりもむしろ天上に近い不思議な歌のリズムだった。そのリズムを追い、またそれをなかば自分で創造しながら、草にうめていた身をもう一度起こす時、私は山々の間に流れる大気が、自分の想念を帯び、また自分の想念は大気の一部分のような気さえするのだ。」「山を下り、谷川の流れが夜のふけるにつれていよいよ強く頭を麻痺させていくような、そんな小屋に最後の夜をすごしながら、帰って行く心と、新しい出発とを夢み、疲れた私を眠らせない。帰って行く心とは、もちろん山を離れて行く淋しい狭い心だが、新しい出発を夢みる心とは、それを打ち消しながら、日ごとの生活に宇宙を感じながら、深い息を明るく吸い込む気持ちである。」
山の中では、自然の中に身を置き、五感を働かせて状況を見極め、行為の決断を強いられることが少なくない。責任は全て自分で負うことになるから、思考の質も変化する。今置かれた状況に感性を研ぎ澄まして、全知全能で臨むという思考回路が働くのだ。やがてそれは、登山という領域固有の非日常的なステージを乗り越えて、日常生活を規定する思考様式へと広がっていく。串田が、非日常的な行為としての登山を「非宗教的な洗礼」として意味付けるのは、このことと深く関わっているのだろう。「行為と思考」、この2つが一体となって繰り広げられる串田のパンセの世界は深い。
「未知の旅へ」といわんばかりの高校時代の気まぐれな思いは、40年近くたった今、このような形で生き続けていることを誰が想像できたであろうか。これが私のパンセ、その原風景である。
*写真は今年の夏、学生時代からの山仲間が送ってくれた槍ヶ岳の様子。学生時代から親しんできた北アルプス山系にある。
* 2013年.ヤマケイ文庫(底本は実業之日本社1972年刊行)
(村瀬@学校長)